
なかじま社会福祉士事務所
中島 啓和さん
プロフィールを教えてください
なかじま社会福祉士事務所を経営する、社会福祉士です。社会福祉士は介護福祉士や精神保健福祉士といった福祉系の国家資格です。
一般的に社会福祉士は福祉施設で利用者やその家族等との相談業務をおこなう仕事ですが、介護保険制度がはじまってから対象者の権利擁護を促進するため、成年後見制度の担い手になれるようになりました。他に成年後見業務を担える専門職は、弁護士や司法書士等です。
成年後見業務を行える社会福祉士になるには、国家資格取得後、社会福祉士会という職能団体に所属し所定の専門的な研修を受ける必要があります。
どうしてその仕事を選んだのですか?
高校生の時に障害者施設のボランティアとして参加しました。それまでの人生の中で得ることのできなかった「自分の存在を人に認められること」が強く感じられました。
高校を卒業してからも、ここにいたいと思い、その施設に勤務しました。就職と同時に短期大学の夜間学部に入学。社会福祉の理論を学びました。
短期大学を卒業してから幅広いボランティアを養成企画、実践する社会福祉協議会に入職しました。
社会福祉協議会で勤務しながら通信大学で社会福祉士に必要な単位を取得。国家試験を受験し社会福祉士になりました。
社会福祉協議会で地域福祉業務を行うなかで、成年後見業務のできる社会福祉士に出会いました。「対象者に自分の全てを使ってお手伝いできる」成年後見業務の素晴らしさに惹かれたことを思い出します。
なかじま社会福祉士事務所を2008年に開業。現在9年目を迎えています。
成年後見業務は、これまでの間に54名の成年被後見人等の対象者と出会い23名の方と別れました。現在31名の成年後見人として、その方の「ふつうのくらし」を支えています。
社会福祉協議会での業務は一つ一つ、とても楽しいものでしたが、自分は、純粋にケースワークをやりたかった。ケースワークは「個別援助技術」と訳されるように、その人そのひと、一人ひとりの目の高さに合わせた生活のお手伝いをするものです。
その方の生活課題を抽出し、行政で行われるサービスや介護保険、ボランティアによるサービス等を調整していき、実践。評価し、また新たな課題を見つけていきます。
成年後見業務は、そうしたケースワークに加え、福祉サービス等の利用契約の締結事務や、財産管理が加わり、まさしく「代理人」の役割を果たしています。
失敗談はありますか?
2008年に「成年後見業務だけで事務所を経営していきたい。」と開業してから、実際そうなるまでに丸3年かかりました。本業を続けるため、今まで経験のない分野での「カン」を養うためにアルバイトをしながら生活していきました。
特に開業当初は、妻と1歳の子どもを抱えていましたので、その時は苦しかったのを憶えています。
成年後見業務では、特に財産管理面では1円の使途不明金があった場合でも家庭裁判所から解任を言い渡され、すべての仕事を失います。また、そのことは社会福祉士法の信用失墜行為に該当するため資格も剥奪されます。
失敗は許されません。
その仕事をしてい良かったと思う時はどんなですか?
守秘義務があるので、個別の対象者について、お話しすることができないのが、とても、とても残念です。それぞれが、テレビのようにドラマチックに展開しています。
成年後見人は成年被後見人の生活を創り、寄り添い、記録に残す。その方の「伝記」を作るような仕事だとも思っています。
その方の一冊の本の終わりのほうで成年後見人が登場し、いちばん終わりのページも、あとがきも成年後見人が作ります。
個人的には、ご自宅や、社会福祉施設、病院などで生活されている方のもとへ定期的に訪問し、その生活を共にしている感覚。その中で対象者の希望をみつけカタチにしていく。その対象者の感情が共有できることが、すごく心地よく感じます。
皆さんに伝えたい事や今後目指している事について教えてください。
成年後見人が仕事として成り立っている時代の背景には、家族のもつチカラや役割が弱くなっていることを裏付けます。
なかじまの家族は、日々、家族力強化に努めておりますので、みなさまも身近な家族に優しくしてあげてください(笑)。
「遠くの親戚より、近くの専門職」
なかじまの身に余る成年後見業務の依頼を受け、2015年に成年後見業務のできる一般社団法人「後見けやき」を有志で立ち上げました。
「地域であたりまえに暮らすこと。」をこれからもお手伝いして、それぞれの「『ふ』つうの『く』らしの『し』あわせ」を創造してまいりますので、ご縁がありましたら、よろしくお願いいたします。
ブログ:おとうさんは社会福祉士 http://nawootousan.blog70.fc2.com/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
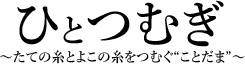








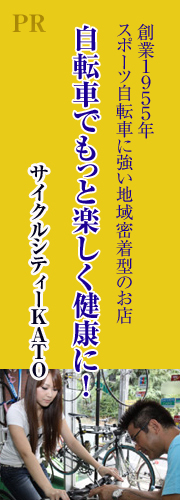

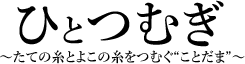
この記事へのコメントはありません。